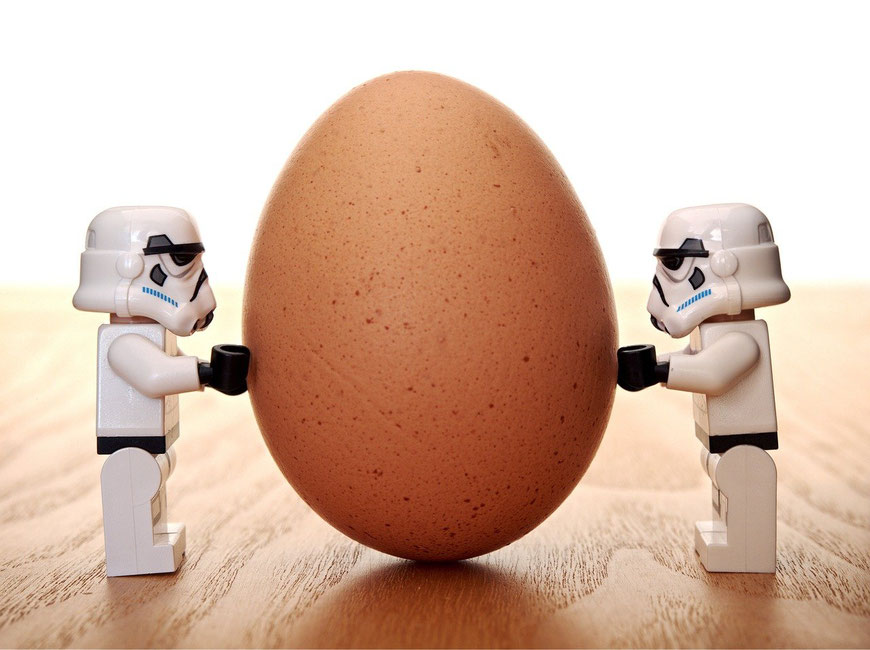
推している間は「自分の価値」を示さなくていい
今は、「何をするか、何者になるのか」が過剰に求められる時代ともいえます。
子どもの頃から「将来は何になる?」とずっと聞かれ続け、大人になると「あなたは何をしているのか?」と問われ続ける。そんなしんどさを、多くの人が無意識のうちに感じているのではないでしょうか。
けれども、「推し」ができれば、そこに向き合っている間は自らの価値を行動で示す必要がなくなります。何も持たない素の自分でいていいと思える。ゼロの状態で心をほどいていられる。この心境は非常にウェルビーイングといえるでしょう。
その対象がスポーツチームの人もいれば、特定のブランドになる人もいるでしょう。応援するチームが連敗続きでも、ずっと変わらずに熱狂的なファンであり続ける。Appleの新製品が発売されたら無条件で手に入れる、いわゆるApple信者のような人たちも同様です。
一方で、アイドルの「推し」を持つ人が多いのは、「歌」と「踊り」という身体感覚に基づくウェルビーイングの原型をアイドルのパフォーマンスが有しているから、という理由も考えられます。
ある部族が外から来た人を受け入れる際に、歌って踊る儀式を行うことは世界中に共通して見られる傾向です。言語が通じなくても、歌って踊る姿を相手に見せることは、「あなたに敵意はない」という姿勢の表明になります。
また、人間の脳は踊っている人の姿を見ているだけでもセロトニンやドーパミン、エンドルフィンなどの幸せホルモンが分泌されることが科学的に確認されています。
加えて、動きが揃ったダンスパフォーマンスは、見る側の脳に快感をもたらします。また、歌う側としても歌っている最中は脳内の二酸化炭素濃度が高まるため、幸せホルモンがドバドバと分泌されます。そう考えるとアイドルのライブに参加してそのパフォーマンスを見ることは、ウェルビーイングの究極形のような時間ともいえるでしょう。
このように、「推す」という行為はあらゆる面で人生に多大なウェルビーイングをもたらしてくれるのです。
能力が足りなくても「替えの利かない」存在
いつからか日本では、ソロアイドルよりもグループアイドルのほうが圧倒的に支持されるようになりました。その要因はすでにさまざまなところで分析されていますが、ウェルビーイングの見地からも、グループアイドル人気を語ることはできます。
ソロアイドルは一人である以上、アイドルとして存在し続けるために「する」こと、つまり歌唱力やダンスなどのアーティストとしてのスキルを磨いて武器として身につけていかなければなりません。つまり、ひたすら上を目指すしかない。
一方、グループアイドルは発進段階で、とにかく「一緒にいる」ことがほぼ強制的に求められます。「いる」から始まる関係性は、必然的にドラマが起こりやすい。そこには何が起きるかわからないサプライズの予感が満ちています。個々のパフォーマンスよりも、集団の関係性に期待と関心が集まるのです。
グループアイドルと同じく、バンドもまたメンバーそれぞれの関係性というストーリーへの期待と憧れがファンの心を強く惹きつけます。
第一級の腕前と才能を持つスタジオミュージシャンが結集したからといって、人気バンドにはなれません。完成度の高いドゥーイングな人たちを集めても、その腕前に感心はしても、感動までは生まれないのです。
何かを「する」ために集まると、私たちはすぐに「あいつはいつまで経っても使えない」「最近入社してきたあの人は意外と使える」という見方で相手をジャッジしてしまいがちです。
けれども「いる」から始まったメンバーであれば、その人の替えが利かないことが何よりも大事なのであって、演奏の腕はさして重要ではありません。その人として存在してくれたらそれでいい。ファンはきっとそんな思いでステージを見るはずです。
これは芸人さんの世界でも同じでしょう。吉本新喜劇のベテラン芸人さんたちの中には、いつ登場しても同じことしかしない。けれどもいるだけで存在感があるし、お客に喜ばれる。そういった域に達している芸人さんは少なくありません。噺家も同様。年老いて声が聞き取りにくくなっても、芸がグダグダになっても、それでも愛され、記憶に残るのです。
愚者を責めない寛容さ
日本のフィクションでは昔から、許しと寛容が繰り返し描かれてきました。
落語で間抜けなことをする役回りの与太郎は、どれだけ周囲に迷惑をかけ、騒動を引き起こしても「しょうがねえなあ」とすぐに許されるのが常です。愚者を責めない文化・風土は、かつての日本には確かにあったのでしょう。
愚かな行為をした人をさげすみ、疎み、排除する。そうすることで一時的な安堵を得る人も多いでしょう。けれどもその先には殺伐とした世界しかありません。
能力で人を見る行為は何をもたらすのか
努力をすれば報われる。努力は必ず実を結び、幸せな人生を約束してくれる。かつて私たちはそれが正しいことだと教わってきました。
けれども近年、アメリカを中心に他人を能力でジャッジすることへの批判が出始めています。ハーバード大学のマイケル・サンデル教授も、著書『実力も運のうち 能力主義は正義か?』(早川書房)で能力主義に疑問を投げかけています。そして有能か無能かというものさしで他者をジャッジする風潮が行きすぎると、社会に分断が生み出されます。同時に、この路線を突き進むほどに、ウェルビーイングが遠ざかっていくことも間違いありません。
この説を体現しているユニークな国内企業があります。家電量販店のケーズデンキは、競争激化が続く業界で「がんばらない経営」という方針を打ち出しました。残業なし、ノルマなし、無理をしない。こうした戦略によってどんな変化が起きたのかというと、販売員がのびのびと丁寧に、本音で接客できるようになったのです。
ノルマがないから焦らなくていい。商品のいいところも悪いところもフラットに本音でお客さんに伝えられる。この方針が大当たりしました。丁寧な接客によって高額商品の売上が伸び、コロナ禍にもかかわらず2021年3月期の連結決算は過去最高益を記録します。
ではこのまま右肩上がりを目指すかというと、その方向へは行かない。なぜなら「がんばらない」ことを継続するからだ、と同社は宣言しています。
競争が厳しい時代だからこそ、「あるがままでやっていく」ことを大切にする。苛烈な競争が繰り広げられる外資系企業とケーズデンキであれば、おそらく後者の社員のほうがよりウェルビーイングな人生を送っているのではないでしょうか。

コメントをお書きください