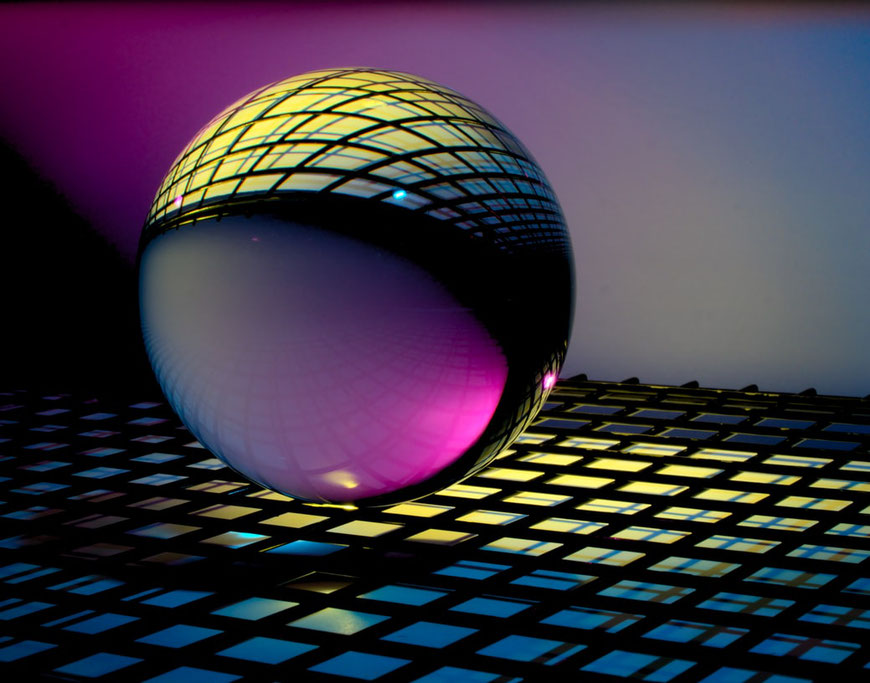
巨額資金を調達するスタートアップが続出
一方、スタートアップ企業への投資も急拡大している。ニューヨーク証券取引所では今年「SPAC(特別買収目的会社)」と呼ばれる特殊な上場手法を使って、一度に数億ドル(数百億円)もの巨額資金を調達する量子スタートアップ企業が続出。これらを中心に量子コンピューター関連の投資額は、優に15億ドル(1500億円以上)を超えるなど史上最大に達した。
難解・深遠な量子力学を理論的な礎とする量子コンピューターの研究開発は、アイデアが発案された1980年代から長年にわたって、物理学者らがその実現可能性などをめぐって知的な議論を戦わせては楽しむ「科学の楽園」であった。
それがいつの間にか、そしてなぜ巨大IT業界の中核プロジェクトにして、生き馬の目を抜くウォールストリートにおける格好の投資対象へと変貌を遂げたのか。一大ブームを迎えつつある量子コンピューター開発の歴史や現状などを探ってみることにしよう。
そもそも量子コンピューターとは、20世紀初頭の欧州を中心に最先端の物理学として確立され、原子核や電子などミクロ世界を説明する「量子力学」を計算の基本原理とする次世代計算機だ。
ちなみに「量子」とはもともと「エネルギー量子」から生まれた物理の専門用語で、ミクロ世界ではエネルギーが連続的に変化するのではなく、飛び飛びの離散値をとることに由来している。その最小単位が「量子」と呼ばれるものだ。
この「量子」ならでの特徴を生かした本格的な量子コンピューターが開発されれば、その計算速度は異次元の領域に達し、スパコンをはじめ従来の計算機がまるで「原始時代の石器」にも見えてしまうほどだといわれる。
1980~90年代、英国のデイヴィッド・ドイッチュ博士をはじめ先駆的な物理学者らが、量子コンピューティングを実現するための具体的な方式やアルゴリズムなどを提案した。いずれも「量子並列性」と呼ばれるミクロ世界の不可思議な現象を、超高速計算の理論へと応用したものだ。
「白でもあり、黒でもある」という状態を利用
私たちの生きるマクロな日常世界では、白はあくまで白であり、決して黒ではない。しかし量子力学によって説明される極小の世界では、「白は白であると同時に、黒でもある」という奇妙な状況が成立する。
要するに、1つのモノが同時に幾つもの異なる状態を取りうる。これが「量子並列性」と呼ばれる現象だ。
量子コンピューターでは、この量子並列性を利用して、1台のコンピューターの内部に自らの分身を無数に作り出す。これら無数の分身が協力して1つの仕事をこなすので、その結果として超高速の計算が実現されるのだ。
量子コンピューターの活躍が期待される分野は、いわゆる「NP困難(Non-deterministic Polynomial-time hardness)」などと呼ばれる特殊な問題群だ。
例えば、セールスマンが多数の都市を一度ずつ巡って元に戻る巡回コストの最小値を計算する有名な「巡回セールスマン問題」など、一般に「組み合わせ最適化」と呼ばれる問題が「NP困難」の一例として、よく引き合いに出される。
一見、簡単そうだが、都市の数が3つ、4つ……と増えていき、ある段階に達したところで、計算量が爆発的に増加するので手に負えなくなる。
これらは、計算方法がわかっても、それに従って実際に計算しようとすると現在最速のスパコンを使っても有限の時間内には解けない問題だ。このような難問は、IT、金融、自動車、化学、医薬品、航空、軍事などさまざまな産業分野に多数存在し、それらを解くために異次元のスピードで動作する量子コンピューターの出現が待たれているのだ。
一方、もしも本格的な量子コンピューターが実現されれば、公開鍵暗号RSAなど従来の暗号技術が容易に破られてしまうため、ITや金融業界のほか、国防・諜報活動など安全保障の分野でも深刻な懸念を呼んでいる。
このため各国政府は量子コンピューターでも破ることのできない量子暗号技術の開発に躍起だ。
また他国に先駆けて本格的な量子コンピューター開発に成功した国は、産業競争面での強力なアドバンテージを得ることから、いわゆる「経済安全保障」の最優先課題ともなっている。
こうした量子コンピューターの中核となる要素技術が「量子ビット」だ。
パソコンからスパコンに至るまで従来のコンピューターでは、そのデータを表現する各ビットが0か1かのいずれかを表す。これに対し、量子コンピューターでは、従来のビットに対応する量子ビットが(ある確率分布に従って)0と1の両方の状態を取り得る。この奇妙な二重性が(前述の)量子並列性を生み出す源となっている。
量子ビットを実現するには、「超電導」や「電子のスピン」、あるいは「光の偏光」などさまざまな物理現象が利用されるが、現時点で最も広く使われているのは「超電導」を利用した方式だ。
「超電導量子ビット」はNECが開発
この超電導量子ビットは1998年ごろに、当時日本のNECに所属していた中村泰信氏(現在は博士、東京大学教授)、蔡兆申博士(現在は東京理科大学教授)らの研究チームが開発した技術だ。
ここで「超電導」とは、特定の物質において、その電気抵抗が低温でゼロになる現象のことだ。電気抵抗がゼロになると、ループ(環状)回路において電流が永久に流れ続ける。このループ電流は非常に安定しているので、これを用いれば量子コンピューターに必須の量子ビットを表現できると考えられた。
NECで開発された超電導量子ビットは、素材的にはアルミニウムと酸化アルミニウムなどから構成され、それらが互いに接する「ジョセフソン接合」という仕組みによって実現される。
アルミニウムは絶対温度1K(-272.15℃)近辺で超電導に達するが、そこにはジョセフソン接合によって右回りと左回りの電流が共存する奇妙な量子状態が出現する。
このうち「左回り」の電流を0、「右回り」の電流を1と定めれば、0と1が重ね合わさった量子ビットを表現できる。このような超電導量子ビットは、量子コンピューターを実現するうえで最も安定した素子として評価され、その後も各国で研究が進められた。
2009年には、アメリカのイェール大学やカリフォルニア大学サンタバーバラ校などの研究チームが、半導体関連のシリコンやニオブなど標準的な材料や技術で超電導量子ビットを実現した。これによって「夢の量子コンピューターを本当に作れそうだ」ということを世界に示した。
その結果、2010年以降、IBMやインテル、グーグルをはじめアメリカの巨大IT企業はいずれも自社の量子コンピューターを開発する際に、この方式を採用することとなった。
他方、日本メーカーは超電導量子ビットのように中核的な要素技術で先行しながら、肝心の実機開発でアメリカ勢に後れを取ってしまった。
今は試験機レベルの製品だが…
現在、IBMやマイクロソフト、アマゾンなどは、自主開発あるいはスタートアップ企業などから調達した量子コンピューターを、クラウド・サービスとして提供している。これを通じてさまざまな業界の企業に量子コンピューターを使ってもらい、その普及を図っている。
日本で今年7月、川崎市の「かわさき新産業創造センター」で稼働を開始した量子コンピューター「IBM Quantum System One(IBM Q)」は、東京大学を中心に産業界と共同で設立した「量子イノベーションイニシアティブ協議会」が各界企業による活用を促していく。
同協議会には金融や自動車、エレクトロニクス、化学をはじめ産業各界を代表する主要企業や大学など14団体が名を連ねている。
例えば、金融機関ではポートフォリオの最適化やリスク管理、自動車メーカーではEV用電池の開発や渋滞回避、化学メーカーでは画期的な新素材の開発などに量子コンピューターが大きな力を発揮すると見られている。
ただし現時点のIBM Qはわずか27量子ビットと、実用機というより試験機レベルの製品だ(この点は後述するアメリカの量子スタートアップ企業の製品も同じ)。したがって協議会の主な目的は、将来量子コンピューターが本格的に普及する時代に備え、今から使い始めることで量子コンピューターに習熟した人材の育成や情報交換を図ることだという。
そうした中、IBMはすでにプロセッサ技術では、冒頭で紹介した127量子ビットの「イーグル」の開発に成功し、来年には433量子ビットの「オスプレイ」、翌2023年には1121量子ビットの「コンドル」をリリースする計画だ。
一般に量子コンピューターがスパコンをはじめ既存のコンピューターを圧倒的に凌駕する「量子超越性」を達成するには、最低でも数百万個の量子ビットが必要と見られている。
しかし、たとえ1000量子ビット程度でも、「AI(人工知能)」や「化学」など一部分野では量子コンピューターが(超越性とまではいかないまでも)優越性を示すようになるとの見方もある。
このためIBMのコンドルがリリースされる2023年は、量子コンピューターが実用化に向かうターニング・ポイントになると、同社の上級副社長・研究部門責任者であるダリオ・ジル博士は考えている。
一方、マイクロソフトは2014年ごろから、理論物理学が予言する「マヨラナ粒子」と呼ばれる謎の物質に基づく独自の量子コンピューター開発を進めてきたが、最近この粒子に関する研究論文が撤回されたのを契機に開発は難航している模様だ。
同社は現在、アメリカのIonQやカナダのD-Wave Systemsなどスタートアップ企業が開発した量子コンピューターを、「Azure Quantum」と呼ばれるクラウド・サービスとして産業各界の企業に提供している。
700億円以上を調達したIonQ
このうちIonQは、アメリカのメリーランド大学などで開発された「イオン・トラップ」と呼ばれる独自技術に基づく量子コンピューターの開発を進めている。今年10月には「SPAC」と呼ばれる手法を使ってニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場し、約6億5000万ドル(700億円以上)を調達した。同社の時価総額は約20億ドル(2300億円以上)に達する。
また同じ月に、アメリカの量子スタートアップ企業リゲッティ・コンピューティングもSPACでNYSEへの上場を果たし、約4億3500万ドル(約500億円)を調達した。同社の時価総額は約46億ドル(約5300億円)だ。
最後にアメリカのアマゾンは、IonQやリゲッティ・コンピューティングなどが開発した量子コンピューターを、「Amazon Braket」と呼ばれるクラウド・サービスとして提供している。
さらに今年11月には、カリフォルニア州に「AWS Center for Quantum Computing」と呼ばれる研究所を開設し、ここで量子コンピューターの自主開発にも乗り出した。IBMやグーグルと同じく「超電導量子ビット」方式のマシンを開発していく計画だ。
アメリカでは新旧入り乱れた企業が量子コンピューターの開発を加速しているのに対し、日本企業はその利用に徹するというのでは心もとない。ここからは日本勢の奮起が望まれるところだ。

コメントをお書きください