
集めて売るか、分けて売るか
この世界に存在する財は、「集めると高くなるもの」と「分けると高くなるもの」が存在している。
例えば、集めると高くなるものの典型は「土地」である。日本を代表するデベロッパーである森ビルのビジネスモデルは、10年以上の時間をかけて、細かい民家が密集したエリアの土地を買い集めていき、再開発を行い、巨大ビルを建てるというものである。
なぜ土地を集めると高くなるか、それは、狭い土地であれば2階建ての民家しか建てられないところ、まとまったエリアがあれば50階建てのビルを建てられる、即ち48階分は生み出されるキャッシュフローが増大することになるからである(土地の行政区分等については捨象し単純化しているが、ご容赦いただきたい)。
一方、分けると高くなるもの、の代表例は、例えば肉や魚である。
肉や魚は、塊やサクの状態よりも、切り身になっているほうが値段が高い。実際のところカットする工数というのは大したことがないのだが、一手間かかっているという認知が働き、高い支払いを消費者が許容するわけである。
これに限らず、世の中の大半の財は、「まとめると高くなる」「切り分けると高くなる」に分割できるので、目の前の財に対してもその分類ができないか、思考実験してみることが肝要なのである。
横浜市立大学の経営史学者であった森泰吉郎およびその息子である森稔を中心として「港区の大家」とも言われ、六本木ヒルズなどを保有する数少ない非財閥系大手不動産会社である。森稔の弟の森章が率いた森ビル開発は後に森トラストとして独立した。
森ビルのビジネスモデルは、低層密集地域を高層ビルに変えることで、圧倒的なレバレッジがかかるが、その分再開発を取りまとめるのに時間がかかる。森ビルが非上場である理由の1つに、再開発事業はタイムスパンの長い事業であるため、短期での資本収益性が求められる上場はそぐわないと経営陣が考えているであろうことも、大きな要因であると思われる。
ビジネスを行うときに見逃せないのが、当然、種銭の大きさの効果である。
種銭がデカいことの効果は非常にシンプルで、例えば自動車会社を作ろうと思うと、工場から含めて数千億円という巨額の資金が必要で、結果としてグローバルで見ても数十社というオーダーに競争相手が限定される。
つまり、資本が大きければ大きいほど、参入できるプレイヤーが限定され、結果として競争相手の数が減るわけである。
また、製造業においては多くの場合、投下資本量によって工場がどの程度効率化できるかが決まる。すなわち、資本の量が決定的な競争優位の要因になることが多いのである。
単純に説明すると、これがスケールメリットである。
その反対もある
一方、スモールメリットというのも存在する。
例えば人材紹介エージェントは、1人の凄腕エージェントが成約報酬200万円×20人で年間4000万円の売り上げを立てることは可能である。このエージェントが、本社機能を作らずに、自宅マンションを本社としてビジネスを行っていけば、4000万円がほぼまるまる自分のポケットに入るわけである。
しかし、この会社を組織化し、本社機能を作るとする。たいてい、雇い入れるエージェントは本人よりもかなりランクが落ちるエージェントである。当然、人件費のほかに、指導にかかる時間、オフィス費用、PCなどの備品費用などが増大し、基本的に利益率は逓減するモメンタムが働く。
つまり、個の力で食べていくことができる類のビジネスは、強いプレイヤーが1人で個人商店として営業するのが一番効率がいいのである。これがスモールメリットだ。
ベンチャーを興すとき、商売を始めるとき、あなたが大富豪の息子でもない限り、基本的には資本がほぼゼロという状態からスタートする。
その場合、スケールメリットではなく、スモールメリットが働くビジネスを行うのが原則なのである。
ハイクラスの人材紹介エージェントでは、採用される人材の年収の30〜35%程度を人材紹介料として支払うのが一般的である。求職者の獲得から企業への紹介まで、個人のスキルに依存する部分が多く、大手で修業した人が独立することも多い業態である。
保険の営業や、人材紹介エージェントなど、①個人で営業することができ、②仕入れの支払いが後払い可能/無料、③1件あたりの成約単価が高いビジネスは、その性質上、凄腕営業マンが1人で独立する形で成功することが多いビジネスである。
「すし」もまた、「まとめると高くなる」商品の代表例である。
すしは、冷静に考えると「魚の切り身一切れ+少量のご飯」の塊でしかないのだが、高級店になると一貫1000円というところも珍しくない。
また、回転ずしが「一皿100円〜」と書いてあると安く感じるが、そもそも「魚の切り身一切れ+少量のご飯」の塊の値段としては、妥当ないし少し高いといったところである。
さて、「すしはなぜ高いのか」について、「仕込みに手間がかかっている」であるとか、「技術が必要」などの解釈をするのは可能だが、実はこれは幻想であるように思われる。
「魚の切り身+少量のご飯をすしと定義する」「すしは高い、というイメージが成立している」という前提条件のもと、すし屋は高い値段を取ることに成功しているのである。
冷静に考えると、例えばラーメン屋であっても仕込みに10時間かける店はたくさんあるだろうし、ゆで具合のコントロールや湯切りなど細かい技術によってそれなりに味は左右されるだろう。
価格はカテゴリーの「イメージ」次第
実際のところ、「すし屋といえば1万円くらいはかかるだろう」「ラーメンであれば1000円程度で食べたい」というその商品カテゴリ固有のイメージができており、それに合わせて価格帯が決まっているのが、実際のところであるように思われる。
つまり、支払う金額というのは、前提となる商品カテゴリのイメージにかなり左右されていて、実際の中身について価値を詳細に検討して購入する人はほとんどいない、ということなのである。
逆に言うと、ビジネスを立ち上げるうえで、「高級とされるカテゴリに勝手に入り込む」という手法は極めて有効である。
具体例を挙げると、明らかに築地なのに「銀座東」と名乗っているマンションや、客観的に見ると立ち飲みバルでしかないのに「カジュアルフレンチ」などと名乗っている店舗がその典型である。
もちろん、多少のツッコミが入る可能性はあるが、それでも「築地」「立ち飲みバル」と名乗ったときと比べて、2〜3割はプレミアムが乗せられている、というのもまた実態であろう。

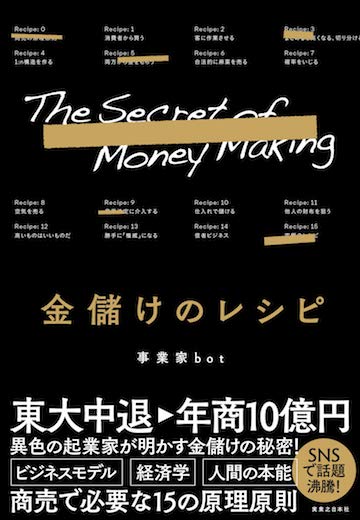
コメントをお書きください