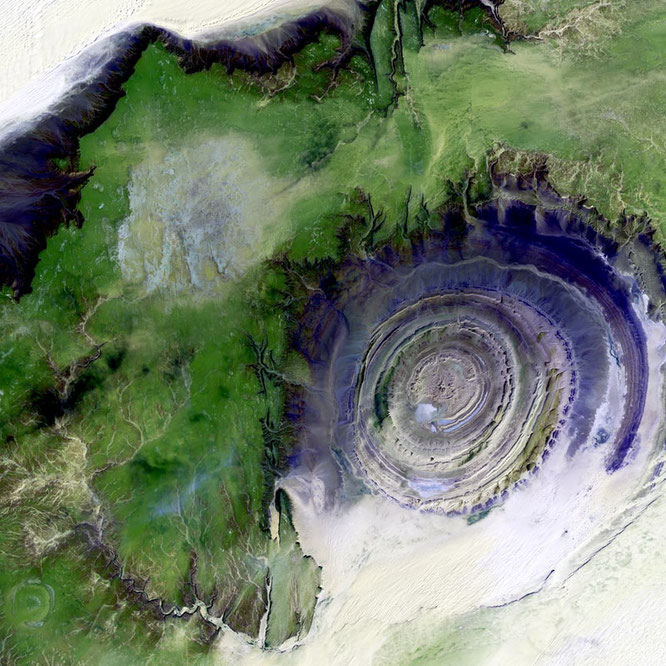
「小さなかけらになって死んでいく」細胞を発見
人間の細胞が「きちんと死んでいく」様子については、1972年、オーストラリアの病理学者、ジョン・カーらが偶然、見つけました。病気になった組織を顕微鏡で観察していると、「小さなかけらになって死んでいく」細胞を見つけました。
私たち人間の体は、「細胞」という基本単位からなっていますが、この細胞の中に、さまざまな指令を出す「DNA(遺伝子)」があり、カーは、「細胞はもしかして自発的に死んでいるのではないか。これはDNAが指令を出しているのではないか」と考えました。
カーはこれをアポトーシス(apoptosis)と名付けました。ギリシャ語で“apo”は「離れる」、“ptosis”は「落ちる」という意味で、英語でいえば”falling off”。細胞が小さなかけらになっていく様子を、秋に木の葉が落ちる様子になぞらえたのです。科学者も、わかりやすく伝えるにはどうしたらいいか、と知恵を絞っているのですね。
当時、細胞の死を巡っては、細胞が膨張し、破裂して死を迎える「壊死」=ネクローシス(necrosis)という言葉で一括りにされていましたが、カーらの発見は、この細胞の死に、新たな分類を加えました。しかし、当時はあまり注目されなかったようです。
その後、がんやアルツハイマーといった重篤な病気に、このアポトーシスが重要な関わりをもっているのではないか、という仮説が立てられ、2002年、アメリカの生物学者ロバート・ホロヴィッツらが、体長約1ミリの線虫の細胞死のメカニズムを研究しました。
その結果、「器官発生とプログラム細胞死の遺伝制御に関する発見」でノーベル医学・生理学賞の受賞につながったのです。
研究というのは、いま役に立たなかったり、脚光を浴びなかったりしても、その後、何かに役立つ可能性があるからこそ尊いのです。いま役立つものばかりを求める日本政府の姿勢は……おっと、話がそれましたね。
細胞の自発的な死=アポトーシスを観察すると、細胞が死んでいくとき、自らの生命の素であるDNAをきちんと切断していることがわかりました。とすると、アポトーシスの本質は「DNAを切断して、消去する」ということになります。
アポトーシスの異常によって起こる病
このアポトーシスに異常が起きるとどうなるか。わかりやすい例で言えば、「がん」です。がんは「本来死んでいく細胞が死ななくなり、どんどん増えていく」病気です。このため、治療には、細胞にアポトーシスを思い出させる薬が必要になります。
一方、肝炎やエイズ、アルツハイマーは、アポトーシスが「進みすぎる」ために起こると言えます。つまり、細胞がものすごいスピードで死んでいくため、臓器や脳が機能不全になるということです。このため、こちらはアポトーシスを抑制し、うまく働くように促す薬が必要となります。
このようにアポトーシスは、人間の病気、つまり長生きできるか、はたまた病気で死んでしまうか――に大きく関わることがわかります。それでは、なぜこのシステムが生まれたのでしょうか?
地球上で生命は約38億年前に生まれました。この生命誕生から約18億年間、実は「死」そのものが存在しなかったのです。これはどういうことでしょうか。
その当時いたのは、オスもメスもない、ただ1個の細胞だけでできている「単細胞生物」です。細胞の中には、1組のDNAがあります。単細胞生物は、このDNAを複製、つまりコピーして増えていきます。コピーですから、元のものと変わらず、死ぬこともありません。数を増やすためには、これがもっとも効率の良い方法だったのです。
しかし、約20億年前。地球に初めて巨大な大陸が出現し、地球環境は激しく変化します。海で暮らしていた単細胞生物たちは、栄養分が極度に不足し、絶滅の危機に瀕したのです。そこで単細胞生物はどうしたのか。なんとDNAの複製をやめ、単細胞生物同士で“合体”したのです。
最新の研究では、栄養分が不足する環境の中、“合体”することで、お互い足りない栄養素を補おうとした、と考えられています。これまでの生き方を180度変えた単細胞生物たちから、「生きたい!生き抜くぞ!」という声が聞こえてきそうですね。
こうして、“合体”することにより、単細胞生物たちは、体内にDNAを2組持つようになります。すると、くっついたDNA自身も、一部の組織が入れ替わるなど、変化が起きました。いわば「親」とは違う、新しい生命が誕生したことになります。私たち人間の仕組みと似ていますから、“先祖”が誕生した、とも言えますね。
さらに6億年後には、単細胞生物たちが進化します。“合体”した単細胞生物同士が、さらにつながりはじめました。細胞が複数ある多細胞生物の始まりです。
やがて進化を遂げ、海で暮らすもの、陸に上がるもの、空を飛ぶもの……さまざまな多細胞生物が誕生しました。もちろん、私たち人間も多細胞生物です。多細胞生物になったことで、あらゆる環境に進出でき、生き残る可能性が高くなったのです。
私たち人間のDNAにも、こうした「厳しい環境に耐えて生き抜く」ことが組み込まれているかもしれません。だとすれば、新型コロナウイルスの厳しい時代も、きっと生き抜けるはずです。勇気を持ちましょう。
多細胞生物に進化して起きた宿命
さあ、生命誕生から約24億年の旅を経て、「なぜアポトーシスが生まれたか」の話にたどり着きました。実はこれは多細胞生物に進化したことで起きた“宿命”と言えそうです。
多細胞生物になることで、同時に、数多くのDNAも存在することになります。しかし、このDNAは、食物の中の発がん性物質やストレスなどにより傷つきやすく、この傷が時問と共に蓄積されていくことが研究でわかっています。
例えば、生殖を担う細胞が傷を負うと、それは子ども、さらに孫に引き継がれていくことになります。すると集団のなかに傷が蓄積される、これを「遺伝的荷重」といいます。種が絶滅する可能性が非常に高くなります。
これを避けるためには、ある一定の時間を生きてDNAが傷ついた個体は「消去する」システムをつくっておけばよい、となります。ある程度の期間が経つと死ぬプログラムをDNAに書き込み、細胞が死ぬように指示すれば、「遣伝的荷重」による種の絶滅を防げるわけです。
これが、アポトーシスが生まれた理由と言えるのです。寿命は、種の絶滅を防ぐため、気の遠くなるような長い時間をかけて獲得した、現時点では抗うことのできない、私たち人間の宿命なのです。
もし、細胞にアポトーシスのシステムがなく、仮に寿命が300歳だとしたら……。
例えば100歳まで生きたとしても、残り200年。考えただけでも、何か空虚なものに思えてしまいませんか。
『旧約聖書』に書かれた人間の寿命=120年、ではないですが、そういった限りがあることによって、「自分はどう生きればいいのか」「自分は何者か」と深く考えることにつながり、一日一日がかけがえのないものになると言えますね。
ちなみにこの人間の寿命=120年と聞いて真っ先に思い出すのが、1986(昭和61)年、120歳で亡くなったと「された」鹿児島県徳之島出身の泉重千代さんです。
「された」としたのは、その後の調査で本当は105歳だったのではないか、となっているためです。
着替えや布団畳みを1人で行っていた
とはいえ、当時はこの泉さんの長寿にあやかろうと、多くのメディアが取材したり、観光客も訪れたりして、こんな記録が残っています。
極め付きがこの会話です。
年齢を重ねても、明るく、こういうユーモアを持ちたいところです。

コメントをお書きください