
チャットやメール特有の「伝わりにくさ」に要注意
チャットやメールでの指示は通りにくい。相手の反応が見えないのでどこまで伝わっているか、わからない。聞いたことに対する返事が、正しく返ってこない。こんな悩みを抱えていませんか?
「だからやっぱり、出社して直接指示するか、最低でも電話で話さないと」と思っている方も多いのではないでしょうか。
チャットやメールには、コミュニケーションを快適にする書き方の「コツ」があります。
そのコツを覚えると、口頭によるコミュニケーション以上の効果を得ることができます。指示や依頼の内容が明確になり、伝え漏れがなくなるからです。
では、どのようにすれば、コミュニケーションミスを防ぐことができるのでしょうか。
僕が100冊以上もの「文章術について書かれた本」を読み、その内容を調査・分析してみた結果、
・「文章のプロが大切にしている書き方のコツ」には共通点がある
・「誰でも、早く、上手な文章を書く」ための絶対ルールがある
ことがわかりました。
今回は、その絶対ルールの中から、テキストコミュニケーションを円滑にするために最も大事なポイントを3つ、紹介します。
ほんの1分間、自分の入力したテキストを見直すだけでも効果のある方法です。
業務上の指示や依頼をするときに最もNGなのは、1つの文にあれこれと内容を詰め込むことです。
次の文を見てください。
【わかりにくい例】
新商品の販促会議は火曜日の午前9時から本社3階の第1会議室で行い、オンラインでの参加の方には新商品のサンプルを事前に配布しますのでプロモーション部・堀越にご連絡ください。
-----
この文は文字数が多い上に、いくつもの内容が詰め込まれているので、「何をどうすればいいのか」がわかりにくくなっています。注意深く読まないと、「誰がプロモーション部の堀越さんに事前連絡をすべきなのか」、読み間違える人が出てしまう恐れがあります。
事務連絡は、あくまで読み手が「パッと見てわかる」ように書くことが大切です。
1つのことを伝えたら、文を終わらせる
読み手に即座に理解できる文章を書くポイントは、
「ワンセンテンス・ワンメッセージ」
ようするに、
「1つの文で伝えることを1つに絞る」
ことです。
・文……句点「。」(マル)で区切られたもの。2つ以上の文の連なりが「文章」
この原則に従って書き替えると、次のようになります。
【改善例1】
1月12日(火)午前9時から、新商品の販促会議を行います。場所は本社3階の第1会議室ですが、オンラインでの参加も可能です。オンラインでの参加希望の方は、事前に新商品のサンプルを配布します。プロモーション部・堀越にご連絡ください。
-----
改善例1では、1文目で開催の日時を、2文目で場所を、3文目以降でオンライン参加の際の注意事項を伝えています。
これならば、別の作業の合間にパッとこの事務連絡を見た人でも、必要な情報を正しく把握できるはずです。
「1つのことを伝えたら、文を終わらせる」。この意識を持つだけで、テキストコミュニケーションでの誤解を防ぐことができます。
チャットやメールで指示をする場合、文章の「見た目」を気にすると、さらに読みやすくすることができます。
「見た目を気にする」とは、
「空白行や改行を積極的に設ける」
ことです。
私たちは、文章の塊ごとに意味を区切って捉える習慣があります。
ですから、文章を意味ごとに区切ると、読み手の理解をうながすことができます。
先ほどの【改善例1】に「見た目」の要素を加えると、次のようになります。
【改善例2】
1月12日(火)午前9時から、新商品の販促会議を行います。
場所は本社3階の第1会議室ですが、オンラインでの参加も可能です。
プロモーション部・堀越にご連絡ください。
-----
改行と空白行をうまく使う
【改善例2】では、
・文章ごとに改行を加える
・前半の会議開催のお知らせと、後半のオンライン参加希望の人だけに向けたメッセージとの間に空白行を入れ、区切りを設ける
ことで、日時や場所をより明確に示しています。
会議の日時や場所の連絡の場合、「見た目」を重視すると、より一層、「読みやすく、正確な文章」をつくることができます。
【改善例3】
新商品の販促会議のお知らせです。
・日時:1月12日(火)午前9時から
・場所:本社3階の第1会議室(オンラインでの参加も可)
-----
箇条書きにすれば、書き手自身も情報を整理できるため、情報の書き洩らしを防げます。
仕事の速い人の中には、チャットやメールの内容を事前に決めてから書くのではなく、「考えながら書く人」「すぐに書き始める人」もいます。
「考えながら書く人」や「すぐに書き始める人」は、接続助詞の「が」を多用しがちです。
・接続助詞……前後の文をつなぐ助詞。
接続助詞の「が」には、おもに「2つ」の用法があります。
① 単純接続……文と文を単純につなげる
② 逆接……反対のことをつなげる。接続詞の「しかし」 と同じ用法
注意が必要なのは、単純接続の「が」です。単純接続の「が」は、前後のつながりのない文でもくっつけてしまうので、多用すると1文が長くなったり、論理が破綻しかねません。
次の例を見てください。
【わかりにくい例】
1月12日(火)に開催予定の新商品の販促会議ですが、予想以上にリモートでの参加者が増えそうとのことですが、事前に配布するサンプル数を事前に把握したいと思っていますが、いつ頃までに必要数をお知らせいただけますか。
-----
意味を推測してもらいながら読んでもらおう
この例文では、
「事前に配布するサンプルの、必要な数がわかるのはいつか」
という骨格に、補足情報をすべて「が」で接続した結果、文章全体がわかりにくくなっています。
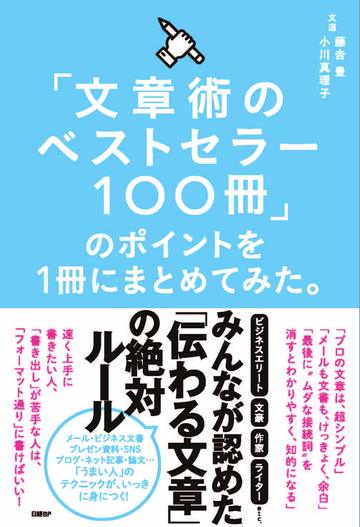
「が」で文をつなぐと、読み手は「単純接続なのか、逆接なのか」を推測しながら読まなくてはなりません。「意味を推測しながら読ませる」というワンステップが、読み間違いや勘違いの原因となります。
読み間違いをなくすためには、単純接続の「が」を使わないこと。「が」は、「逆接に限って使用する」ようにしましょう。
以下の「改善例4」は、単純接続の「が」を省いた例です。
単純接続の「が」を省いた結果、1文が短くなり(ワンセンテンス・ワンメッセージになり)、「何について話しているのか」「なぜその情報がほしいのか」が一目瞭然です。
【改善例4】
1月12日(火)に開催予定の新商品の販促会議は、予想以上にリモートでの参加者が増えそうだと聞きました。
配布するサンプル数を事前に把握したいと思っています。いつ頃までに必要数をお知らせいただけますか。
-----
文章のプロの多くが指摘する3つのポイント(①ワンセンテンス・ワンメッセージ ②意味の切れ目ごとに改行や空白行を入れる ③文章をやたらと「が」でつながない)を意識するだけで、
「必要な情報が的確に伝わる」
「書くスピードが上がる」
ようになります。
これらのポイントを取り入れて、チャットやメールでのコミュニケーション、ひいてはリモートワークやオンライン会議を、より快適・円滑にしていきましょう。

コメントをお書きください