
「インフルエンザより怖くない」は間違い!
2019年に中国・武漢で発見された新型コロナウイルス感染症「COVID‐19」は、「SARS-CoV-2」と呼ばれるコロナウイルスが原因で起こる感染症です。
感染してもその症状は、無症状者から軽症者、中等症患者、重症者や犠牲者までさまざま。また、無症状者や、症状が出る2日程度前から感染者がウイルスを出してほかの人に感染させることもあります。発症日の前後くらいが最もウイルスを多く外に出すとされます。この発症前の人や無症状感染者が気づかずに社会活動を続けてウイルスを広げてしまうことが、感染の拡大を止められない原因にもなっています。
さらに、感染から症状が出るまでの潜伏期間が長く、1~14日間(多くは5日間)くらいです。発症から1週間程度は発熱やせきなどの風邪症状が続き、そのまま治っていく患者が全体の80%程度とされます。
20%の人は呼吸困難や咳などで、肺炎症状が悪化し、中等症・重症患者として入院対象になります。高齢者や糖尿病・高血圧・慢性腎臓病などの基礎疾患のある人、肥満の人、喫煙歴のある人、悪性腫瘍のある人、妊婦などが重症化しやすいといわれています。
一方で、前述のように感染しても80%の人が無症状か、もしくは風邪症状で治ってしまうため、「新型コロナウイルス感染症は季節性のインフルエンザよりもたいしたことない」と言う人もいます。
しかし、
② 発症の2日前からウイルスを体外に排出して感染源になる可能性がある
③ 感染しても無症状のことが多く、その人もウイルスを排出してほかの人を感染させる可能性がある
④ 体外での生存期間が長い
⑤ 急速に悪化することがある
⑥ 2020年10月時点では確定した治療法がない
⑦ ワクチンが存在しない
などの点でインフルエンザ以上に厄介です。
新型コロナウイルスは、生活環境の中でインフルエンザウイルスなどよりも長く生きられるということもわかっています。例えば、ステンレスの表面では2~3日間、段ボールには24時間、プラスチックでは3日間も、不活化されません。
また、10~20代の若者が重症化した例もあります。基礎疾患がなくても、大量にウイルスに曝露されると重症化しやすくなるとも考えられています。
治ったと思っても終わらない後遺症の怖さ
新型コロナウイルスは、症状の重症化だけでなく、その後遺症にも注意するべきです。治ったと思った後も、後遺症によってその後の生活にまで支障を来すことがあるのです。
イタリアで143人の元患者に行われた調査では、回復後(発症から2カ月後程度)も87%の患者が何らかの症状を訴えたといいます。倦怠感や呼吸苦の症状のほか、関節痛、味覚・嗅覚障害、めまい、聴覚障害、なかには脱毛などの報告もあります。
これは重症者だけではありません。アメリカからの調査によると、感染からの回復者270人のうち35%に何らかの後遺症がみられ、18~34歳の「若い世代」でも26%が普段の健康状態ではないと回答。後遺症は2つ以上の複数症状がみられる場合もあります。
国からの治療費補償の有無についても問題ですが、何より後遺症が残ると身体的・精神的な苦痛が長く続くことになります。
「息切れが激しくなった」
「目や口が乾燥する」
「なんだか疲れやすい」
「耳がよく聞こえなくなった」
「せきがまだ続く」
「食欲が戻らない」
「関節が痛い」
「毛が薄くなってきた」
「嗅覚が戻らない」
「記憶に障害が……」
年代に関係なく発症する合併症
新型コロナウイルス感染症は症状が出るだけでは終わりません。合併症が起こることが少なくないのです。具体的には、呼吸不全や不整脈、肺塞栓症や脳梗塞などの静脈血栓塞栓症、川崎病の症状に類似した多系統炎症性症候群などが報告されています。
合併症は、高齢者や基礎疾患のある人だけではなく、健康な若者や小児に起こった事例もあります。そのため、どんな合併症が起こりうるのか、年齢層にかかわらず知っておくべきです。
まず、息切れなどの症状を引き起こす呼吸不全です。急性呼吸窮迫症候群は、重症患者にみられる主な合併症です。肺炎などにより呼吸困難を起こした直後にみられることがあります。
ほかにも、脈拍が不安定になる不整脈、ショック状態、血圧低下などの心血管系の合併症もあり、急性心障害などを引き起こすケースも。呼吸が速くなったり乱れたりすると、心臓の動きも乱れます。肺のガス交換の機能が低下すると、体中に血液と酸素を送り込むために、健康なときよりもより多く動く心臓にはそれだけ負担がかかります。
肺塞栓症や急性期脳卒中などの、血栓塞栓症も約16%報告されており、致死率との高い関連性があります。これは、血栓(血液の塊)が血管を詰まらせてしまうことで、脳の血管を詰まらせると脳梗塞に、肺の動脈を詰まらせると肺塞栓症になります。新型コロナウイルス感染症の重症例において、とくに血栓症との併発が多くみられています。
子どもは重症化しにくいと思われがちですが、子どもがかかりやすい合併症もあります。
それは、発症の9割近くが4歳以下で、全身の血管に炎症が起きてさまざまな症状が出る川崎病に似ています。川崎病は、熱、両眼球の結膜の充血、真っ赤な唇といちごのようにブツブツの舌、体にできる赤い発疹、手足の腫れ、首のリンパ節の腫れ、以上のうち5つ以上の症状がみられれば診断されます。
まずはかからないことが大事!――対策方法まとめ
新型コロナウイルス感染症の症状についてみてきましたが、まずは感染しないように対策を取ることが大事です。
感染対策として、手を衛生的に保つことはとても効果的です。対策として手洗いとアルコール消毒を行うことが知られていますが、手洗いと消毒では目的が異なります。手洗いは洗浄、アルコール消毒は消毒のためです。手洗いでもある程度の細菌やウイルスを流し落とせますが、消毒することでより安全になります。
そのほか、感染しないための対策方法をまとめました。
①人混みに行かない
最も怖いのは、感染している人と知らないうちに接触してしまうこと。
満員電車のような換気しづらい場所は、空気が滞留するためウイルスが漂っている可能性も高くなります。
②手洗いを欠かさない
手にはウイルスがつきやすいため、せっけんを使い入念な手洗いを欠かさないようにしましょう。また、携帯電話もウイルスが多くついています。こまめに消毒してください。
③温湿度管理の徹底
温度は20~25℃、湿度は50~60%くらいで調整するのが最適といわれています。家に加湿器がない場合には、濡れたタオルをかけておくだけで多少湿度は上がります。
④外出時はマスクとメガネを着用
飛沫感染防止、また顔を触る機会を減らすために、マスクやメガネをすることは非常に有効です。マスクの着脱をする際には、マスクのひも部分を触るようにしましょう。
【ポイント】
⑤外から帰ってきたら……
・消毒する
帰宅したらカバンやスマホなど、洗濯できないものはできるだけ消毒するようにしましょう。手も外出の都度、消毒します。
・着ていたものは玄関に置いておく
着ていたコートにもウイルスは付着します。玄関に置いておき、ウイルスを部屋の中に持ち込まないようにしましょう。

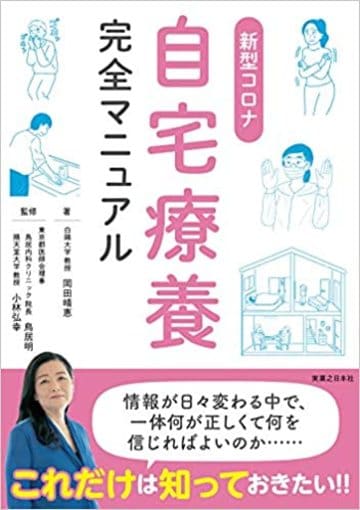

コメントをお書きください