株の指標(PER, PBR, PSR と EPS, BPS と ROE, ROIC, ROA)
指標には意思が入り込む。
意図を読み解き、紛れ込む悪意を排除して賢く立ち回ろう。
それぞれの指標が何を評価しているのか、簡単に整理してみた。
また、「指標の重要度」を解説しているものが少ないため、今の状況を踏まえながら、「どの指標を見るべき」か実例を交えて解説してみようと思う。
PER, PSR, PBR と EPS, BPS の関係
下図は各指標の関係性を表す。
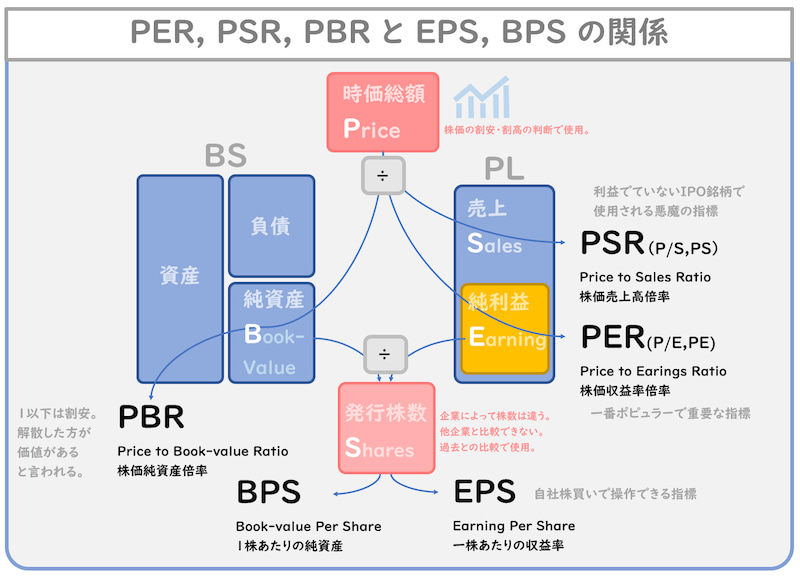 左にBS、右にPLを配置。上に時価総額、下に発行株数を配置。
左にBS、右にPLを配置。上に時価総額、下に発行株数を配置。
線は評価項目との指標の関連を示す。
始点が分子、中継点が分母、終点が算出指標を示す。
指標の詳細は以下の通り。
-
PER(Price to Earings Ratio)
株価収益率倍率:収益に対する株価の大きさ
=時価総額÷収益 -
PBR(Price to Book-value Ratio)
株価純資産倍率:純資産に対する株価の大きさ
=時価総額÷純資産 -
PSR(Price to Sales Ratio)
株価売上高倍率:売上に対する株価の大きさ
=時価総額÷売上高 -
EPS(Earnings Per Share)
1株あたりの収益
=純利益÷発行株式数 -
BPS(Book-value Per Share)
1株あたりの純資産
=純資産÷発行株式数
ここで、注意すべきは、指標には意思が入るという事。
発行株式数を分母に持つEPSやBPSは、自社株買いで、株数を減らせば、数値を恣意的に上げることができる。
この指標には業績以外に、経営者の意思が入る。良く言えば、株主への配慮と株価を重視しているという市場へのメッセージ。悪く言えば、EPSや株価と連動する経営者の報酬へのたくらみが反映される。(なお、EPS,BPSは株数に依存するため、他社との比較ではなく、過去との推移で確認する指標。)
EPSと連動する役員報酬の規定
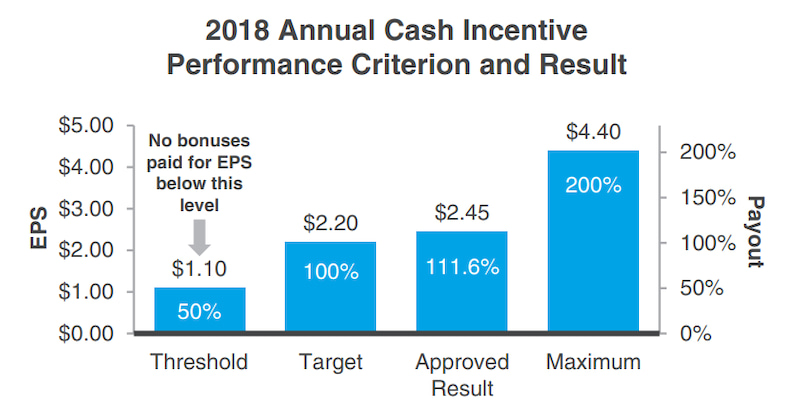
出典:チャールズシュワブIRより
例えば、EPSが2倍を達成できれば、役員ボーナスは2倍になると役員報酬の規定に記載されている。株を減らしてEPSを上昇させるインセンティブが働く報酬体系になっている。
PSRは、まだ利益がでていない企業を評価する際に使われる、PERの代替手段の指標。資金を集めたいIPO企業の経営者や、株を売りたい証券会社・アナリストの立場から発信される悪意が紛れ込む指標である。
ただし、PSRも使い方によっては有益である。
「利益が出ていない・一時的に収益性が悪くなった」企業の推定PERをPSRから逆算する方法もある。(参考)

PBRは、株価が芳しくないときに注目され、「解散して現金化し、株主に還元した方が価値がある。」と物言う株主(アクティビスト)が批判時に使用する指標である。割安株を探す際にも使用される。
以上を踏まえると、
PERで業績と株価の割高・割安を判断し、
EPSで業績と経営者の意思を読み取るべきだと考える。
(例としてチャールズシュワブをだしたが、良い会社だと思っています。)
ROA, ROE, ROIC の関係
図は各指標の関係性を表す。
線は評価項目との指標の関連を示す。
始点が分子、中継点が分母、終点が算出指標を示す。
指標の詳細は以下の通り。
-
ROA(Return on Asset)
総資産利益率:総資産に対する利益の大きさ
=当期純利益÷総資産 -
ROE(Return on Equity)
自己資本利益率:自己資本に対する利益の大きさ
=当期純利益÷自己資本 -
ROIC(Return on Invested Capital)
投下資本利益率:投下資本に対する利益の大きさ
=税引き後営業利益÷有利子負債+株主資本
税引き後営業利益(NOPAT)とは
NOPAT(Net Operationg Profit After Tax)
営業利益から税金を引くことで、支払利息を包含した利益を示す。
ROICの分子は何が妥当か?については、立場の違いで議論がある様子。
ROA,ROEの指標は、いずれも、稼ぐために使ったリソースに対してのリターンの高さを評価する指標である。
稼ぐために使ったリソースを、
「資産」で評価するのがROA、
「株主資本」で評価するのがROEである。
これらの指標には欠点がある。
- ROAの欠点
- 稼ぐために使用されていないAssetも含む。
- ROEの欠点
- 稼ぐために調達した負債が考慮されない。
これらの欠点を補う指標がROICである。
-
ROIC(投下資本利益率)
=税引き後営業利益÷(有利子負債+株主資本)
稼ぐために使用したリソースとして、
「有利子負債+株主資本」を含んで評価する指標である。
ROIC(有利子負債を含んだ評価)の重要さを理解して貰うために、近年の自社株買いの状況を示してみよう。
10年間の自社株買いの割合
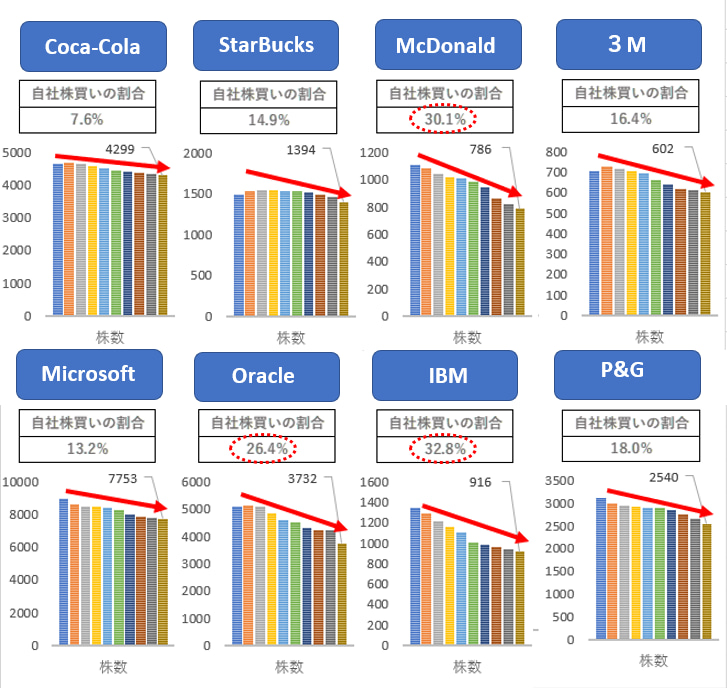
上記は過去10年間の各社の自社株買い割合である。
10年間で30%の株数を減らしている企業も存在する。
現在は、低金利を背景として、有利子負債で資金を調達し、自社株買いを行う会社が多い。この結果、「発行株数は減り、EPSは自動的に上昇」し、「Equity(株主資本)は減少し、ROEも自動的に上昇」する状態にある。従って、EPSの上昇は、割り引いて評価すべきだし、リターンは負債も含めて評価すべきである。
もう少し詳しく、実際の企業で各指標の動きを確認してみよう。
3M(MMM)の場合
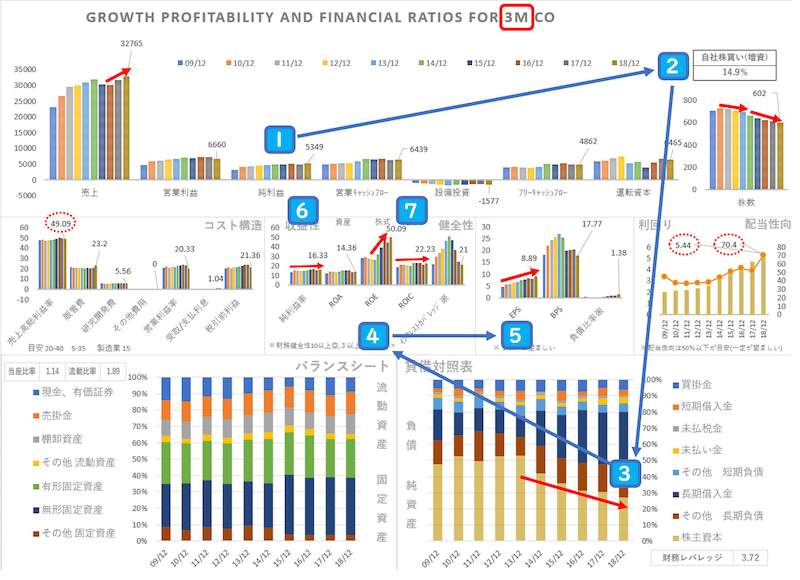
3M Company(スリーエム)は世界的化学・電気素材メーカー。
ポストイットが有名。
上図の番号に従って指標の動きを説明する。
- 純利益は微増か横ばいぐらい。
- 自社株買いをしている。
- その結果、株主資本が減少し、長期負債が増加。
- 株主資本(Equity)が減少し、ROEが上昇
- 株式数(Share)が減少し、EPSが上昇
- 利益率は増えていない。
- ROICは増えていない。
純利益は微増か横ばいぐらいで、利益率が改善しているわけではない。
ROE、EPSの上昇は、自社株買いを表しているため、本来の業績を見る場合は、ROICの方が実態に近い。(ROAも実態に近いうごきになっている。)
つまり、「うちの会社は、EPSが上がり続けています。」とアピールしていても、実態は稼ぐ力が強まっているわけではなくて、自社株買いで株数が減らしたことでEPSが上昇しているという事もあり得るわけだ。(分かり易い財務諸表の例として3Mを出しただけで、3Mは良い会社だと思っています。)
ちなみに、一般的に、どの指標が見られているのか、Google Trendsで確認してみよう。
PER, PSR, PBR, EPS, BPS はどれくらい見られているのか
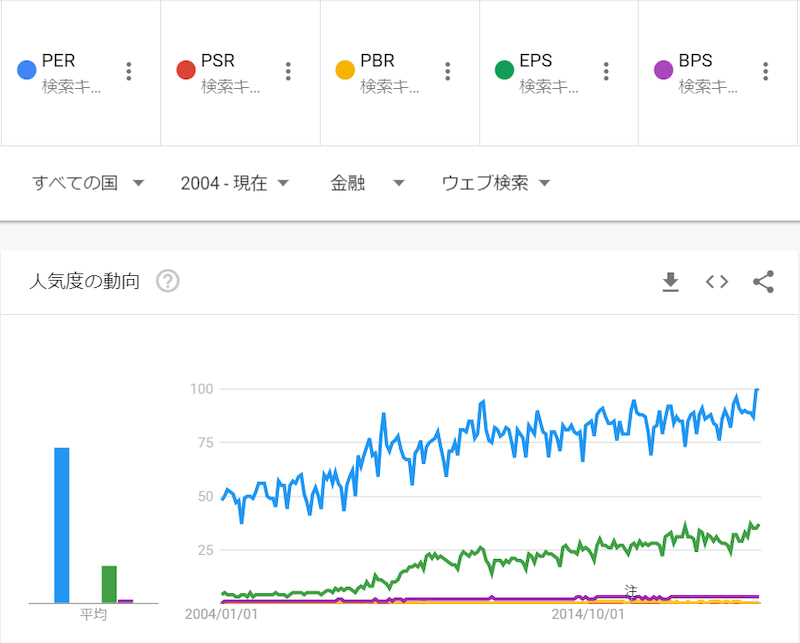
出典:Google Trendsより
Google Trends の人気動向をみると、PERとEPSの2強である。(EPSってバブル崩壊後ぐらいから伸びていて、投資家の視点をPERからずらす意図が感じられる)
ROE, ROA, ROIC, (EPS) はどれくらい見られているのか

出典:Google Trendsより
前述のグラフと比較できるようにEPSを加えている。
現状は、EPS、ROE、ROA、ROICの順で注目されている。
ROICは算出の困難さもあり、注目度は低いが、今まで解説した通り、自社株買いで負債を増やしている今こそ、注目すべき指標だと考える。
まとめ
まとめると、
PERでは業績と株価の割高・割安を、
EPSでは業績と経営者の意思※を読み取ると良いと思われる。
(※株主への配慮、自社株買い方針、株価に対する市場へメッセージ)
また、金利が低下している状況下では、
ROEには自社株買いの影響がでやすいため、
併せて「ROICやROA」を確認するか「負債の増加」に注意した方が良いだろう。
このように「指標の評価対象」や「低金利の情勢」との関連を理解し、経営者や証券会社・アナリストの裏の意図を理解すれば、指標に振り回される事なく、逆に指標を武器として利用する事ができるだろう。
そして、正確に指標を理解する事で、
誰かが見せたい情報を見させられるのではなく、
自分が見たい情報を見る事ができるようになるだろう。
今回整理した内容が、分析をする際の参考になれば幸いです。

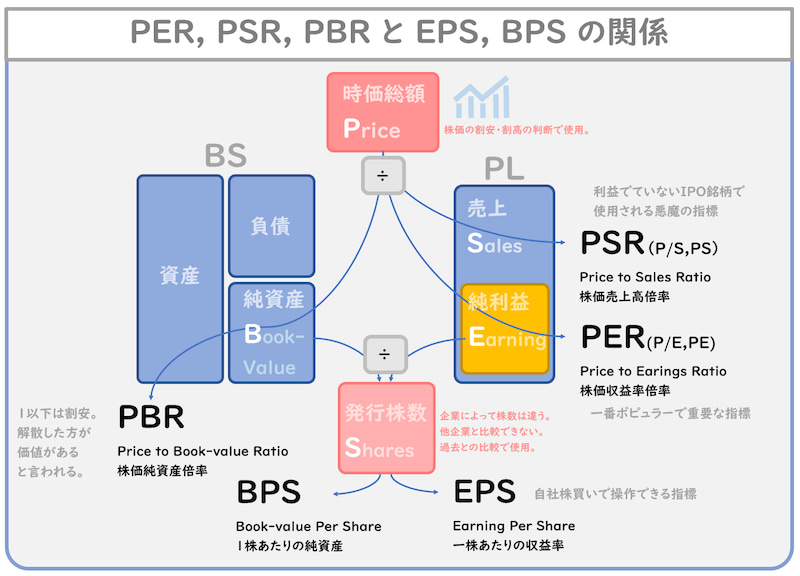
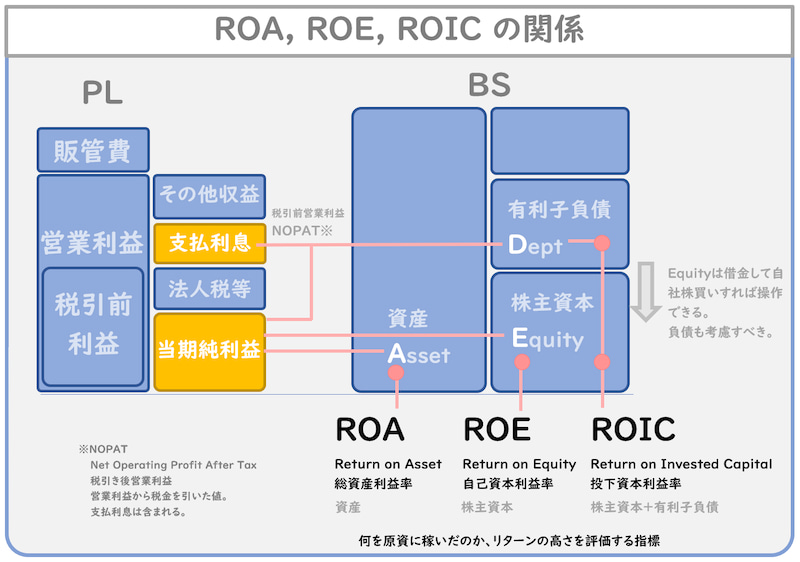
コメントをお書きください